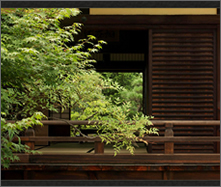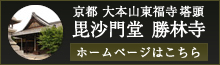京都毘沙門堂 勝林寺と申します。
本日は今が見頃の「有楽椿」をご紹介致します。

有楽椿の名は、織田信長の実弟である織田有楽斉長益が茶席の花として愛用したことに由来していますが、京都では有楽椿、それが江戸では太郎冠者の名で呼ばれるようになりました。安土桃山時代(茶人としては千利休が有名)から江戸時代にかけて、将軍家・公家・大名・豪商など上流階級の間に広まった茶の湯の席で重宝されていました。花は12月から4月頃までと早咲きで開花が長く、一重の中輪ラッパ咲きで、淡紅色に紫を帯びた日本にはない色素を持っています。また、子房には蜜毛があり、レンゲソウに似た微香を有しています。葉は、先端が細長い長楕円形で、葉質は固く、端は鋸歯状になっています。

私の好きな花の一つです。

皆様「有楽椿」をお楽しみいただけましたでしょうか?
境内は写真撮影可能ですので是非皆様もお近くまで来られましたらどうぞ写真に収めてください。
もう一本見ごたえのある椿が御座いますので次回をお楽しみに・・・
勝林寺住職 合掌