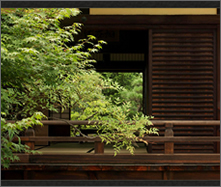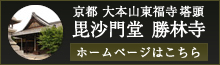京都毘沙門堂 勝林寺と申します。
京都毘沙門堂 勝林寺と申します。
今日は勝林寺の紅葉情報をお伝え致します。境内の一番若い紅葉が赤くなってきました。東福寺も勝林寺もまだ観光客が少ないので写真を撮りに来られる方はチャンスかもしれません。
ツワブキも満開に咲いております

勝林寺住職 合掌
東福寺塔頭勝林寺紅葉2011・10・31
東福寺紅葉2011年10月30日
京都毘沙門堂 勝林寺と申します。
今日は雨がしとしと降っており東福寺・勝林寺もとても苔が綺麗でした。
勝林寺の坐禅体験も満員でした。雨降りでしたのでかなり静かな時間の中、皆様真剣に坐禅をされていました。やはり雨の坐禅はいいですね。
新しい「美守り」もかなり人気があります。前の「美守り」も若干ありますのでどうぞ拝観時以外でも授与致しますので御来寺お待ちしております。
(事前にお電話いただけると助かります。)新しい「美守り」は後日「勝林寺和尚の日記」にてアップ致します。皆様お楽しみにお待ちください。
さて、今日の東福寺の紅葉の様子ですが若干色づき始め・・・という感じです。
まだまだですね・・・
東福寺紅葉
ツワブキ
京都毘沙門堂 勝林寺と申します。今朝はかなり冷え込みました。皆様体調管理にはくれぐれも御注意ください。
もしかすると紅葉も早いかもしれませんね・・・東福寺の紅葉・勝林寺の紅葉もtwitterとブログで、できるだけお伝えしたいと思います。
さて、今回はボチボチ花が咲いてきました勝林寺のツワブキを御紹介致します。
ツワブキキク科 ツワブキ属
開花期:10月中旬~11月下旬
草丈:15~60cm
ツワブキの名前の由来は艶のある葉のフキ、すなわち艶葉蕗(つやばぶき)らしいです。
本州の暖地や九州、沖縄、中国、台湾などに分布する多年草で、厚みのあるフキのような丸い葉っぱを出します。葉の表面には光沢があり美しく、日陰でもよく育つので古くから庭園の下草として利用されてきました。晩秋に花茎を伸ばして一重の黄色い花を数輪~10輪程度咲かせます。花後はタンポポのような綿毛ができて風が吹くとタネが飛んでいきます。(去年、種を植えたら今年芽をだしましたよ。綿毛が飛んであちこちからも芽をだしています・・もしかすると数年後にはツワブキのお寺になってるかもしれません)
葉は緑単色のものだけでなく様々な形の斑のはいるものや、(斑入り種は明るい雰囲気になるので、シェードガーデンに取り入れてもよいのではないかと思います。)表面がくしゃくしゃと縮れたようになる獅子葉と呼ばれるものなどバラエティーに富んだ品種・変種があります。(写真は班入りです。他にも2種類植えてます。是非拝観の時に見つけて下さいね)鉢植えの場合、数年育てていると鉢の大きさに見合った大きさになるというおもしろい性質があります。例えば、小さな鉢に植えると出てくる葉も小さく、軸も短くなりミニ観葉植物のようなコンパクトな鉢植えになります。地植えにすると大人の手のひらより大きな葉になりますが、品種によっては小さな鉢で育てると親指大くらいの大きさまで小さくなるそうです。根の張れるスペースに応じて株の大きさを変えるのかもしれません。草丈が低く、大きな葉が放射状にたくさんでるのでグラウンドカバーにも利用できます。長く伸びた葉っぱの軸の部分は佃煮などに加工され食用となります。
非常に育てやすいので花の少ないこの時期に皆様も育ててみてはいかがでしょうか?
勝林寺住職 合掌
唐橘(百両)
京都毘沙門堂 勝林寺と申します。
今回は2010年勝林寺秋の特別拝観で寺宝の説明をしてくださるガイドさんからいただきました百両を御紹介致します。
百両はヤブコウジ科ヤブコウジ属の常緑小低木です。
本州の茨城県から沖縄にかけて分布し、林の中に自生します。
海外では、台湾や中国にも分布しています。
本来は唐橘ですが別名を百両(ヒャクリョウ)ともいい、おめでたい木とされています。
古典園芸植物の1つで江戸時代に改良が進み、100種もの品種が生み出されたらしいです。
寛政年間には価格が高騰して売買禁止令も出されています。
「カラタチバナの取引価格が百両以下にはならなかったために『百両』と呼ばれることになった」との記述もあります。
樹高は30~50センチくらいで幹は直立するが、万両(マンリョウ)のように上部で枝分かれをしない。
葉は細くて大きな披針形(笹の葉のような形)で、互い違いに生える(互生)。
葉には短い柄があり、縁には波状のぎざぎざ(鋸歯)がある。
開花時期は7月です。
葉の脇に散房花序(柄のある花がたくさんつき、下部の花ほど柄が長いので花序の上部がほぼ平らになる)を出し、淡い黄を帯びた白い花をまばらにつけます。
花弁は5枚で下向きに咲き、花弁の先が反り返りる。萼片は5枚、雄しべ5本、雌しべ1本です。
この花が橘(タチバナ)に似ているというのが名の由来です。
花の後にできる実は球形で、9~10月ころに赤く熟し、翌年まで落ちません。
実が白いものや葉に班の入った園芸品種もあります。
縁起物ですので是非皆さんも育ててみてはいかがでしょうか?

勝林寺住職 合掌